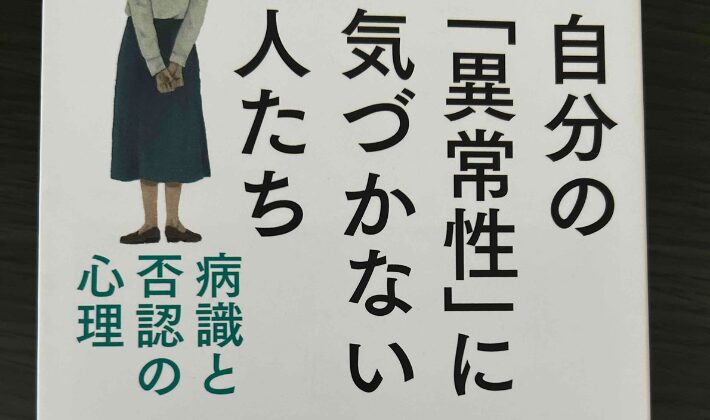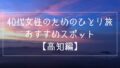おすすめ本の紹介です。
強すぎる被害妄想、執拗な他者攻撃、異様なハイテンション、
引用:自分の「異常性」に気づかない人たち: 病識と否認の心理 西多 昌規 / 文庫裏表紙より
他人をふりまわすサイコパス……
それは許容できる異常性なのか、治療介入すべき異常性なのか?
精神科医である著者が診察室で出会った、さまざまな「自分の異常性」に気づかない人たちを取り上げ、その心の病理と対処法を明らかにする。
診察でのエピソードを通じて、医師の苦悩や精神医療の問題点を浮き彫りにする。
この本は著者の医学博士 西多 昌規さんが臨床経験で出会った様々な症例を紹介しています。
まず読んでいて思ったのは、「大学病院のお医者さんってちゃんと仕事をしてるんだなぁ」ということです。
大学病院というと白い巨塔の白衣をなびかせて巡回してるイメージしかなかったので。←失礼ですよ。
本の中で描かれる、医局の中で同僚の医師と症例について話し合うシーンや、夜勤明けで引継ぎをするシーンなどでリアルな医師の働く姿が見られて興味深いです。
書かれている治療の中には知らないことが多く、例えば病態に深く踏み込むためにこれまでの患者の人生、いわゆる生活史についての情報と解釈が必要だとのこと。
そのために、家族関係や離婚原因などについても聞きとりをします。
まるでドラマのようだと感じました。
プライベートに踏み込むようなシーンは物語を面白く味付けするためにあるのかと思っていたので、現実でも必要な手続きだったとは驚きでした。
他にも知らない治療方法として「症例検討会」がありました。
たくさんの医師が集まり、治療が難渋している患者の症例を話し合って方針を決めるという会です。
ドラマなどでも広い部屋で医師が何十人もいて、大きなスライドを見ながら担当医師から報告を聞く、といったシーンは見たことあります。
驚いたのはその場に患者本人が呼ばれるということ。
もちろん強制ではないらしいですが、医師がたくさんいる中で質問されたり答えたりするようです。
精神に何らかの病状を抱えた人にとってすごく負担になりそうなんですが…
治療方針を決めるために必要なのか…と驚きました。

患者の人たちは「統合失調症」や「うつ病」などを患った人たちです。
エピソードごとに具体的な症状が描かれるので、病気の症例について勉強になります。
エピソードの主人公になった患者以外にも著者が経験した症例なども紹介され、例えば
「行列に平気で割り込んでケンカ沙汰になった」
「街中のメルセデスベンツのエンブレムをすべてへし折ってまわった」
など読んでいて唖然とするような例も紹介されています。
このような話は「病気になった人たち」と自分と一線を引いて読むことも可能です。
しかしその後のページに、病気の診断基準の例が紹介されていて、それを読むと自分にも当てはまるかもしれない…とちょっとドキッとしました。
自分が「異常」になった場合、自分で気づけるものでしょうか。
様々な「異常性」を抱えた人たちとその治療をする医師たちの試行錯誤する姿。
エピソードは小説のように描かれていて面白いので、すごく読みやすく、読み終わるのが残念に感じるほどでした。